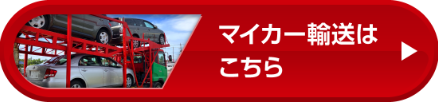物流業界は2024年、大きな転換点を迎えます。働き方改革関連法の本格適用により、トラックドライバーの労働時間に厳しい制限が設けられ、業界全体に大きな影響を及ぼすことが予想されています。
この「2024年問題」は、人手不足やコスト増加など、複合的な課題を物流業界に突きつけています。
本記事では、2024年問題の実態と影響を詳しく解説するとともに、先進企業の取り組み事例や、持続可能な物流体制構築に向けた対策を紹介します。
2024年問題が物流業界に突きつけられる試練
物流業界は2024年、かつてない困難に直面します。
人手不足、法改正、コスト増など、複合的な課題が業界全体を揺るがします。
物流業界に突きつけられる試練は以下のとおりです。
深刻化する人手不足とドライバーの高齢化
トラックドライバーの不足は年々深刻化しています。若手の新規就労者が減少する一方、ベテランドライバーの高齢化が進行しています。2024年には、ドライバーの平均年齢がさらに上昇し、55歳以上の割合が40%を超えると予測されます。
若手ドライバーの確保が難しい理由としては、以下が挙げられます。
- 長時間労働のイメージ
- 他業種と比較して低い賃金水準
- 体力的負担の大きさ
- キャリアパスの不透明さ
法改正による労働時間短縮とコスト増
2024年4月から、働き方改革関連法に基づく労働時間規制が物流業界にも適用されます。
トラックドライバーの時間外労働は年960時間以内に制限され、これまでの長時間労働を前提とした運用が困難になります。
労働時間規制の主な内容
- 時間外労働の上限:年960時間
- 休息時間(勤務間インターバル):9時間以上
- 1か月の拘束時間:原則274時間以内
労働時間短縮は、ドライバーの健康維持や安全運転に寄与する一方、輸送能力の低下やコスト増加をもたらします。
企業は生産性向上と効率化に取り組む必要に迫られます。
これらの課題が物流業界全体に与える影響
2024年問題は、物流業界全体に広範な影響を及ぼします。
以下は具体的な影響です。
物流の遅延と混乱
労働力不足と労働時間規制により、従来とおりの輸送量を維持できなくなります。結果として、配送の遅延や欠航が増加し、サプライチェーン全体に混乱をもたらす可能性があります。
輸送コストの上昇
ドライバーの確保や労働時間規制への対応のため、人件費や設備投資が増加します。これらのコスト増は、最終的に輸送料金の値上げにつながり、荷主企業や消費者の負担増加を招きます。
中小企業の経営圧迫
大手企業と比べて経営資源の乏しい中小物流企業は、人材確保や設備投資の面で不利な立場に置かれます。競争力の低下や廃業リスクが高まり、業界の寡占化が進む可能性があります。
地方経済への悪影響
都市部に比べて人口減少が進む地方では、ドライバー不足がより深刻化します。物流ネットワークの縮小は、地方経済の衰退にもつながりかねません。
消費者サービスの低下
宅配便の配達遅延や再配達の増加、翌日配送サービスの縮小など、消費者の利便性が低下する恐れがあります。
2024年問題を乗り越えるための具体的な対策

物流業界が直面する2024年問題は、単なる危機ではなく、業界全体の変革を促す機会でもあります。以下に、問題解決に向けた具体的な対策を紹介します。
DX (デジタルトランスフォーメーション) による業務効率化
物流業界におけるDXは、業務効率化の鍵となります。具体的な施策として、以下が挙げられます。
デジタルタコグラフの導入
デジタルタコグラフは、ドライバーの運転時間や走行距離を正確に記録します。労働時間管理の厳格化に対応し、効率的な配車計画の立案に役立ちます。
自動配車システムの活用
AIを活用した自動配車システムは、複雑な配送ルートを最適化し、ドライバーの労働時間削減と配送効率向上を両立します。
車両動態管理システムの導入
GPSを活用した車両動態管理システムにより、リアルタイムで車両位置を把握し、急な配送要請にも柔軟に対応できます。
ロボティクス・自動化技術の導入
人手不足解消と作業効率向上のため、ロボティクスや自動化技術の導入が進んでいます。
- 自動倉庫システム
商品のピッキングや仕分けを自動化し、作業時間を大幅に削減します。24時間稼働が可能なため、人手不足の解消にも貢献します。 - 自動運転技術
長距離輸送における自動運転技術の実用化が進んでいます。ドライバーの負担軽減と安全性向上が期待されます。 - ドローン配送
過疎地域や離島など、従来の配送が困難だった地域へのサービス提供が可能になります。
働き方改革と人材確保・育成の強化
技術導入だけでなく、人材面での取り組みも重要です。
- 給与体系の見直し
固定給の割合を増やすなど、安定した収入を確保できる給与体系への移行が進んでいます。 - 多様な働き方の導入
短時間勤務や隔日勤務など、個々のライフスタイルに合わせた勤務形態を提供します。 - キャリアパスの明確化
ドライバーから管理職へのキャリアアップなど、長期的な成長ビジョンを示します。 - 女性ドライバーの積極採用
女性専用の休憩施設整備や、女性向け研修プログラムの実施など、女性が働きやすい環境づくりを進めます。
成功事例から学ぶ、持続可能な物流体制の構築

2024年問題を単なる規制対応ではなく、業界変革の好機と捉えた企業の取り組みから、未来の物流のあり方を探りましょう。
先進企業の取り組み事例
2024年問題に対応するため、多くの企業が革新的な取り組みを始めています。
以下に、3社の先進的な事例を紹介します。
オプティマインド:ラストワンマイル配送の最適化
オプティマインドは、配送業界のDXを推進するスタートアップ企業です。同社は、ドライバー不足や高齢化に対応するため、ラストワンマイル配送のルート最適化サービスを開発しました。
開発プロセスでは、現場ドライバーの声を反映させるアジャイル開発手法を採用。3ヶ月という短期間で高精度な配送ルート算出機能を持つβ版アプリを完成させ、その後もユーザーフィードバックを基に改良を重ねました。
正式リリース版では、サービスの統合によるユーザビリティ向上や視認性の高いUIデザインを実現しています。
さらに、リアルタイムでのルート再計算機能やモバイルアプリ化によるGPSデータ取得の安定化も図りました。オプティマインドの取り組みは、ドライバーの業務効率化と労働時間削減に大きく貢献しています。
ゼンリンデータコム:直感的な配達アプリの開発
ゼンリンデータコムは、地図・位置情報技術を活かし、配達ドライバーの業務効率向上を目的とした「GODOOR」(旧:配達アプリ)を開発しました。
アプリ開発では、利用者の業務フローを考慮したUI/UX設計や繰り返し使用によるメリット創出に重点を置きました。また、住宅地図と連携した重要情報の表示機能や直感的な操作性も重視しています。
開発チームは、想定利用者へのリサーチを実施し、詳細なペルソナを構築。ゼンリン住宅地図上で配達指定時間や宅配ボックスの有無などの重要情報を確認できる機能を実装しました。さらに、荷物の配達ステータスをフリック操作で変更できるなど、ユーザビリティを重視したUIデザインを採用しています。2018年12月のリリース以降も、継続的な改良が進められています。
キリンビール:需給管理・製造計画の最適化
キリンビールは、物流コスト最適化と業務効率化を目指し、2021年に「SCM部」を新設しました。同社は「MJ(未来の需給をつくる)プロジェクト」を立ち上げ、需給業務のDX推進に注力しています。
プロジェクトでは、物流コストの最適化による経済的価値の向上や、物流負荷軽減とCO2削減による社会的価値の創出を目指しています。また、持続可能な業務基盤の構築も重要な目標となっています。
キリンビールの取り組みは、安定供給とコスト最適化の両立を目指すものであり、需給管理と製造計画作成のためのアプリケーション実装が特徴です。
サプライチェーン全体の見直しと連携強化
物流業界単独ではなく、サプライチェーン全体での最適化が求められます。
とくに荷主企業との協業では、納品時間の柔軟化や、パレット輸送の標準化など、荷主と運送会社が一体となった効率化を進めます。
また、物流標準化の推進においては、多様な業界団体が連携し、物流に関する様々な規格やプロセスの標準化を進めています。
たとえば、パレットサイズの統一や、伝票のデジタル化などが挙げられます。共同物流の拡大も進んでおり、競合他社との共同配送や、異業種間での物流リソースの共有など、業界の垣根を越えた連携が進んでいます。
物流業界の未来と展望
2024年問題を乗り越えた先に見える物流業界として、まず考えられるものがテクノロジー主導の物流効率化です。
テクノロジー主導の効率的物流では、AIやIoTを駆使した完全自動化物流センター、自動運転車両やドローンによる無人配送など、テクノロジーが物流の形を大きく変えていくでしょう。環境負荷の少ない持続可能な物流も重要で、電気自動車や水素自動車の普及、モーダルシフトの推進など、CO2排出削減を意識した物流体制が主流になると予想されます。
さらに、労働環境も変化し、短時間勤務、副業・兼業の容認、遠隔操作による物流管理など、柔軟で多様性のある働き方が実現する可能性があります。さらに、国際情勢の変化や感染症リスクを踏まえ、より強靭で柔軟なグローバルサプライチェーンの再構築が進むでしょう。
まとめ
2024年問題は物流業界にとって大きな試練ですが、同時に業界全体の変革を促す機会でもあります。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、ロボティクスや自動化技術の導入、働き方改革と人材育成の強化など、多角的なアプローチが求められています。
また、サプライチェーン全体での最適化や、環境に配慮した持続可能な物流体制の構築も重要な課題となっています。これらの取り組みを通じて、物流業界は従来の課題を克服し、より効率的で柔軟な体制を築いていくことが期待されます。
2024年問題を乗り越えることは、日本の物流業界が新たな時代に適応し、さらなる発展を遂げるための重要なステップとなるでしょう。