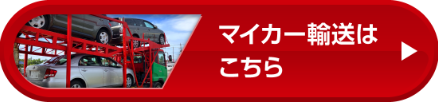車トラブルの筆頭といえば「バッテリー上がり」。バッテリー内の電気がなくなり、車内の電気系統が機能せず、エンジンもかからなくなる状態です。
バッテリーが上がってしまうと、他の車から電力を分けてもらったり、ロードサービスを呼ぶ必要があったりと、初めての経験になると慌てることが多いもの。
そこで今回は、車のバッテリー上がりの原因および対処法と予防策について解説するとともに、バッテリー上がりを防ぐ日常的なメンテナンス方法をご紹介します。イザという時の備えと心構えを持ちつつ、安心したカーライフを送りましょう。
車のバッテリー上がりの原因とは?
車のバッテリーが上がってしまう原因はいくつかありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。以下に挙げるものを普段からやっていないか確認してみましょう。
ライトやオーディオなどの電装品の使用
走行中はエンジンが回って発電するため、電装品の使用によってバッテリーが上がる心配はありません。しかし、エンジン停止後にライトなどを点けっぱなしにしていると、発電されないまま電力を消費し続けてしまい、数時間後には電力を使い果たしてバッテリーが上がります。
商業施設の駐車場でライトを点けたままの車の呼び出しアナウンスがあるのはこのためです。
長期駐車や短距離運転などの車の使用状況
元々乗る機会が少ない趣味の車などを長期間放置していると、自然放電により、いつのまにかバッテリーが上がってしまっていたケースがあります。また、近所のみの移動など、短距離運転を繰り返すとバッテリーに十分な電力が供給されず、徐々に電力を消耗してしまいます。
長期間使用しない車や短距離走行が多い車は、バッテリー上がりのリスクが高くなります。
寒冷地や高温などの気候・環境
バッテリーの性質上、高温・低温の極端な環境下ではパフォーマンスが低下し、気温による影響でバッテリー上がりを起こすことがあります。対象となる季節では、バッテリーの状態に配慮した運転が求められます。
一般的なバッテリーと比べて容量が大きい寒冷地仕様の専用バッテリーを使用するなどの対策を検討しましょう。
バッテリーの劣化と寿命
バッテリーが経年劣化し性能が極端に低下すると、バッテリーが常に電力不足の状態になり、充電効率も悪くなります。そのままにしておくと、いつかバッテリー上がりを起こし、寿命を迎えます。バッテリーの寿命は3〜5年ほどなので、定期的に点検をおこない、早めにバッテリーを交換することをおすすめします。
車のバッテリー上がりのサインを見逃すな!
バッテリー上がりはある日突然起こるイメージかもしれませんが、普段の運転において、ちょっとした異変に気付くことでバッテリー上がりを未然に防ぐことができます。具体的なバッテリー上がりの兆候をご紹介します。
エンジン始動時の異変
バッテリーが弱っていると、車のスターター(始動装置)に電力が供給されにくくなります。そのため、エンジンスタートが遅い、いわゆるエンジンがかかりにくい状態が続きます。
セルモーターから「キュルキュル」と回転音の弱い音がしたら、バッテリーが弱っているサインです。
電装品・その他の動作不良
バッテリーの電力が少なくなると、車内の電装品が動作不良を起こします。ヘッドライト(ハロゲンライト)が暗い、ワイパーやパワーウインドウの動きが遅くなるなどの症状が現れたら、バッテリーの劣化が進んでいる可能性が高くなります。
バッテリーが上がってしまった!その時どうする?

バッテリーが上がってしまうと車を動かせなくなります。バッテリー上がりに遭遇した場合の対応方法を具体的に解説します。
まずは落ち着いて状況確認!安全第一の行動を
車を動かせないと気持ちが焦ってしまいますが、まずは原因を究明し、冷静に状況を整理することが大切です。自分と車が安全な場所にいることを確認し、落ち着いて今後の対応を考えましょう。
原因究明:なぜ車が止まってしまったのか?
過去の点検内容や最近の車の状態から推察し、車が止まってしまった原因を究明します。エンジンがかからない、ライトや他の電装品も機能しない状況であれば、バッテリーが上がっていると判断できるでしょう。
一見バッテリー上がりだと思っていても、発電機やエンジン自体の故障も考えられる場合には、一度専門業者へ診てもらうことをおすすめします。
対処法1:ジャンプスタートを行う
もし他の車による救援が可能で、手元にブースターケーブルがあれば、ジャンプスタートによるエンジンの始動ができます。
ジャンプスタートとは、お互いのバッテリー同士をケーブルで繋ぎ、救援車から電力を分けてもらう方法です。具体的には以下のような方法で行います。
- バッテリー上がりの車両のバッテリーのプラス端子から救援車のプラス端子へケーブルを挟んで繋げる
- 救援車のマイナス端子からバッテリー上がりの車両のボディーアース部分へケーブルを繋ぐ
- 救援車のエンジンをかけ、数分ほどアイドリングさせてから、バッテリー上がりの車両のエンジンをかける
- ケーブルを外す際は、繋げる時と逆の手順で行う
- しばらくエンジンをかけたまま車両を充電させる。もしくは数十分ほど走らせる。
以上がジャンプスタートの方法ですが、ケーブルを繋ぐ順番を間違えないよう注意してください。間違った順番で繋いでしまうと故障や火災の原因になり危険です。
また、救援できる車は、同じ電圧同士(乗用車は12V)かつエンジン車に限ります。ハイブリッド車はバッテリーの構造上、救援車になれません。
同じくハイブリッド車やEVがバッテリー上がりを起こした場合には、素人での復旧は難しくなります。その際はロードサービスに救援をお願いしましょう。
対処法2:ロードサービスの利用
任意保険に付帯しているロードサービスやJAF(日本自動車連盟)へ連絡して救援してもらう方法です。JAFの会員であれば、バッテリー上がりは基本的に無料で対応してもらえます。
救援を呼んでから大体1時間以内には到着し、30分ほどの作業時間で終わることが多いようです。
いざという時のためのロードサービスですので、自分ひとりで対応できない際は遠慮なく救援をお願いしましょう。とにかく自身の安全が優先です。
バッテリー上がりを未然に防ぐ!予防策とメンテナンス

バッテリー上がりを起こさないためにも予防策について知っておくことは大切です。ここでは、普段のバッテリーのメンテナンスも含めて解説します。ぜひ覚えておきましょう。
定期的なバッテリーチェック
定期的にボンネットを開けてバッテリーをチェックする習慣をつけましょう。
また、ディーラーの点検サービスなどを利用して、プロの目でバッテリーの状態を判断してもらうのをおすすめします。整備士から何か提案があれば、参考にしておくのがよいでしょう。
バッテリーに優しい運転習慣
バッテリー上がりを防ぐには、普段の運転におけるバッテリーに負担をかけない習慣も大切です。
- 同時にいくつもの電装品(エアコン・充電・ナビ他)を使用しながら走行する
- 短距離運転のみを繰り返す(周辺近所など)
- アイドリングを長時間行う
- 急発進・急ブレーキが多い、忙しない運転
上記は、すべてバッテリーに負担をかける運転です。心当たりがあれば、意識して改めることでバッテリーの負担軽減に繋がります。
バッテリー交換のタイミング
前回のバッテリー交換からどれくらい時間が経っているか確認しましょう。
一般的なバッテリーの寿命は、もって3〜5年です。もし数年間交換していなければ、一度バッテリーの状態を専門業者にチェックしてもらい、必要ならばバッテリー交換を行いましょう。
バッテリーは消耗品ですので、車の維持・メンテナンスの一環として、消耗品の交換時期を記録しておけば、維持費の管理の面でも安心です。
まとめ
バッテリー上がりはよくあるトラブルだけに、未然に防ぐなどの対策を行うことが可能です。外出時にバッテリー上がりに遭遇した際に慌てないためにも、バッテリーに関する知識があると安心したカーライフを送れます。
バッテリーにおける日々のメンテナンスは、車の寿命を伸ばすことにも繋がります。あなたの大切な車に長い間乗り続けるためにも、これらの知識がお役に立てれば幸いです。