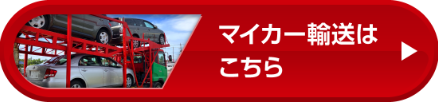日々営利活動を行う企業において、役員用の社用車を検討する際に、車種をどうするか、購入もしくはリースにするかなど、頭を悩ませる事柄が多々あるのではないでしょうか。
企業にとって重要なポジションを占める役員の車は、その会社のイメージを印象づけるため、慎重に選択しなければいけません。
そこで本記事では、役員用の社用車の具体的な選び方や、会社経営において重要な会計・税務処理について解説します。また、役員専属の運転手を外部委託するメリットや契約に関する情報も掲載しています。
役員の社用車選びにおいて、本記事で得た知識がお役に立てれば幸いです。
役員用社用車の選び方
会社の顔でもある役員の車は、その会社の規模や社風、取引先との関係など、考慮するポイントがいくつかあります。関連企業や取引先との間に良い印象を与え、関係を円滑に保つためにも、ある程度の高級感と品格を備えた車がよいでしょう。
なお、下記に紹介する役員用社用車におすすめの車は、2024年5月現在、新車で販売している車種に限っています。
社用車におすすめの車種とその特徴
役員用の社用車には、日本を代表する車メーカーのトヨタ車と、世界から高い評価を受けるドイツ車がおすすめです。
以下、役員社用車として定評のある2大メーカーの車種をいくつかご紹介します。
- トヨタ・アルファード
トヨタの大型クラスの高級ミニバンとして快適さを追求した高い居住性と静粛性は、海外の市場でも高い人気があります。広さと装備が充実している車内において、役員も存分に仕事に集中できるでしょう。
中でも、最上級グレードの「エグゼクティブラウンジ」は、非常に質の高い内装となっており、特にシートに関しては、新幹線のグランクラスに相当する快適性とプレミアム性を備えています。
- レクサスシリーズ

出典:LEXUS
トヨタの高級ブランド車である「レクサス」は、1989年にアメリカで販売をスタートし、その後紆余曲折しながらもレクサスのブランド性を確立させました。日本車がもつ信頼性と機能性を重視したデザインは世界から一定の評価を受け、重役用の車両にふさわしい品格を備えています。
現在レクサスでは、セダン・SUV・ミニバンなど多岐に渡るモデルがライナップされていますが、役員用の車に関しては、やはりセダンタイプが従来から好まれる傾向です。
- トヨタ・クラウン
発売から70年近い歴史をもつ高級乗用車クラウンは、主にミドルエイジを中心に高い評価を得ています。王道の地位にあるクラウンの信頼性は揺らぎがなく、ステータス性も相まって、役員用社用車にふさわしい車といえます。
現在のクラウンは16代目ですが、スポーツ・クロスオーバー・セダンタイプと、どのモデルもモダンでシンプルなデザインと高い走行性能が好評を博しています。
- メルセデスベンツ・BMW
国内におけるドイツ車の位置付けは、走行性能・デザイン・耐久性を含めた非常に高いレベルの外国車として揺るぎない地位を築いています。高級車のシンボル的存在であり、ブランド性も申し分ないことから、重役用の社用車として高い人気を誇っています。
ただし、わかりやすい高級車ゆえ、周りの企業との関係性を考慮し、嫌味にならないように気をつける必要があるでしょう。
購入vsリース、コスト効率がいいのは?
社用車にかかる車両コストは、管理コストと金銭的コストの2つに大別されますが、ここで問題になるのが、車両を購入するか、リースという選択を行うかです。
下記の表にそれぞれのメリットとデメリットをまとめました。
| 車両を購入する場合 | カーリースの場合 | |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
コスト効率の面から見るとリース方式に軍配が上がります。ただし、どちらも一長一短があるため、会社の方針をふまえて検討した上で判断することをおすすめします。
社用車の経費計上と税務処理
ここからは、企業の決算書の中身の車両にあたる費用(経費)計上の方法について解説します。なるべく簡潔な内容に留めますが、企業がスムーズかつ健全な経営管理をする上で、ぜひ参考にしてください。
経費計上の基準と注意点
一口に経費計上と言えども、企業の会計ルールにしたがって正確な処理を怠ると、後々の決算に影響を及ぼす可能性があるため、正しく対応する必要があります。
まずは、簡単に費用計上の基準を説明します。
【車両を購入する場合】
購入年度から6年間(新車かつ普通乗用車の耐用年数)車両取得金額の定額または定率を経費として算入する。
【車両をリースする場合】
毎月かかるリース料を計上する。(減価償却不要)
社用車を購入するか、リース契約をするかで会計処理の方法が異なることに注意が必要です。
また、例外的に「ファイナンス・リース契約」という減価償却が必要なリース契約もあります。リースの種類によっても処理方法が異なりますので、リースの契約内容をきちんと確認して処理方法を決める必要があります。
減価償却資産としての扱い
減価償却の基本は、会社の資産を購入後、1年ごとに費用化した額を計算し、年度ごとに計上しながら資産額を減らしていく会計処理です。「経費計上の基準と注意点」でも述べたように、減価償却資産の耐用年数(6年または軽自動車は4年)は税法によって定められています。
一定期間減価償却を行うことで、法人の所得額が減り、法人税や所得税の納税額が減少することがポイントです。
補足として、4年落ちの中古車を購入する場合、法令上では残り2年分を購入年度に一括で費用計上が可能なため、節税に繋がるという考え方もあります。
役員車ドライバー派遣のメリットと選び方
役員の社用車の運転は本人自身が行う場合と、役員用の専門ドライバーを派遣する会社に外部委託するケースがあります。外部委託をする場合、プロのドライバーが運転を代行するメリットを得るのと同時に、契約を行う上で企業の機密情報を守る体制が求められます。
プロドライバーの派遣とそのメリット
役員専用ドライバーを派遣契約するメリットは主に2つです。
- 採用と研修コストの削減
- プロの運転による安全と安心感を得る
それぞれ解説します。
1.採用と研修コストの削減
自社で専属の運転手を雇う場合、給料以外にも募集・採用広告費、研修費、社会保険料など様々なコストが発生します。外部との派遣契約をすることで、上記のコストを丸々削減することができ、より合理的です。
2.プロの運転による安全と安心感を得る
やはりプロならではの運転スキルによる安心感は、役員の安全を守る上でも得難いメリットだといえます。役員専用のドライバーとなると相応の接客レベルが要求されますので、内部研修をきちんと受けた質の高いドライバーだとより安心です。
安全とプライバシーの確保について
たとえ実績と経験を積んだベテランドライバーであっても、企業役員との間の機密情報の取り扱いには、厳重かつ徹底的な守秘義務が求められます。
機密情報の漏洩リスク対策を充分にした上で、契約する外部派遣会社と話し合いを行い、企業間のコンプライアンスとプライバシーを遵守する旨の確認の徹底が重要です。
外部派遣会社を選ぶ基準として、他企業からの口コミや、ホームページの内容を参考にするのも一つの方法です。教育と研修を高いレベルで実現している外部派遣会社と契約すれば、メリットを最大限に享受することができるでしょう。
まとめ
以上、本記事では役員用の社用車の導入について、選び方や会計上の費用計上の方法について解説しました。車両の経費処理については、慣れていないと複雑なルールだと感じるかもしれませんが、コツさえ掴めばスムーズな実務が可能でしょう。
企業において大切な役員の安全を確保し、良い車選びができるように願っています。