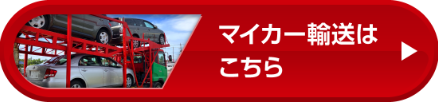「引っ越しをすることになったけど、何から始めたらいいんだろう?」
「役所でどんな手続きが必要なのかな?」
「引っ越し後の手続きも知りたい!」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
引っ越しは事前の準備だけではなく、引っ越し後にも様々な手続きが必要です。
この記事では、引っ越しの準備から引っ越し後の手続きにいたるまでを解説いたしますので、ぜひ引っ越しを検討する際の参考にしてみてください。
引っ越し前の準備
まず、引っ越しをする前に以下の2つの準備が必要です。
・新居探しと契約
・荷造りの計画
それぞれ解説いたします。
新居探しと契約
引越しすることになったら、まずは新居探しから始めましょう。
引っ越し先として考えられるパターンは以下の3つです。
・賃貸マンション
・アパート
・戸建て
物件の契約が賃貸契約なのか分譲で購入するのかによって、手続きが大きく変わります。
物件の種類(賃貸マンション、アパート、戸建てなど)ごとのメリット・デメリット
物件の種類によってメリット・デメリットが存在しますので、それぞれ説明いたします。
賃貸マンションのメリット・デメリット
賃貸マンションのメリット
- 強い構造の物件が多く、防音性や耐震性が高い
- 断熱効果が高い
- セキュリティー面で安心
賃貸マンションは耐久性が高く、地震や火災が発生した時も木造アパートに比べると安全性に優れています。
また、物件によってはオートロックや防犯カメラが備えられているところもあり、セキュリティー面において安心感を得ることができます。
賃貸マンションのデメリット
- 家賃は高め
- 物件の種類が少ない
- 更新料がかかる場合がある
賃貸マンションはセキュリティー面や耐久性など、全体的なコストが上がってしまい、家賃は高めとなる傾向があります。アパートより安全で快適な暮らしを求める場合は、賃貸マンションが向いているでしょう。
アパートのメリット・デメリット
アパートのメリット
- 家賃が安い
- 管理費が安い
- 通気性がよく、カビも生えにくい
住宅コストを下げたいなら、アパートがおすすめです。基本的に2階建てや3階建ての木造アパートが多く、全体的な家賃は安めです。また、管理人や設備も少ないため、マンションに比べると管理費が安い傾向にあります。
アパートのデメリット
- セキュリティー面で不安
- 木造が多く、防音性が低い
アパートのデメリットとして、セキュリティー面に不安があります。マンションのようにオートロックなどはありませんし、アパートの1階にお住まいであれば、空き巣の被害に合ってしまうかもしれません。
また、アパートには木造の物件が多く、隣や上の階の住人の声や足音が気になる物件も存在します。
まわりの生活音に敏感な方などについては、慎重にアパートを選ぶようにしましょう。
戸建てのメリット・デメリット
戸建てのメリット
- 騒音に関するトラブルを防げる
- 自分の敷地内であれば車や物を自由における
- 住宅を自由に作り変えることができる
- 家賃以外の管理費などがない
- ・資産が手に入る
共同住宅とは違い、戸建てにおいてはまわりの生活音や他の住居人とのトラブルに悩まされることはなくなります。また、家の間取りやデザインなどもある程度自由に決められるので、自分がイメージした家づくりをすることが可能です。
また、賃貸であれば家賃を払い続けても自分のものとはなりませんが、戸建てであれば、住宅ローンを払い終わった後は自分の資産となります。賃貸のようにずっと家賃を払い続けるのがいやな方にとっては、戸建てを購入する方がよいでしょう。
戸建てのデメリット
- 簡単に引っ越しができない
- 住宅の管理を自分でおこなう必要がある
- 固定資産税がかかる
- セキュリティー面のリスクがある
戸建ては住宅ローンを組んで購入している以上、簡単に引っ越しができません。今後引っ越しをしたいと思った時にスムーズに手続きができない点はデメリットと言えるでしょう。
また、セキュリティー面にも不安があります。マンションのようにオートロックや防犯カメラがついていないので、セキュリティー面を充実させたい場合は自己負担で準備しなければなりません。
エリア選びのポイント(通勤・通学時間、周辺環境、治安など)
エリア選びは重要なポイントです。職場の距離や近くにスーパーがあるか、治安が悪くないかといったことも考慮する必要があります。
せっかくいい物件を見つけて契約したのに、生活が不便になってしまっては意味がありません。
物件を契約する前に周辺環境などもリサーチしておき、ご自身の生活スタイルに合っているかどうかをよく検討しておくようにしましょう。
内見時のチェックリスト
賃貸物件を検討する際は、実際に気になる物件に足を運んで内見することが重要です。
室内の間取りや周辺環境など、内見の際には以下のチェックリストを参考にしてください。
| チェック項目 | 確認事項 |
|---|---|
| 部屋の広さ | 家具や家電をおくスペースは充分か確認 |
| 間取り | 寝室やリビングの広さなどは問題ないか確認 |
| 日当たり | 周辺に日差しをさえぎる建物などがないか確認 |
| 室内のにおい | 変なにおいやタバコのにおいなどはないか確認 |
| 通信環境 | 携帯の電波がきちんと入るか確認 |
| 収納場所 | クローゼットが広く、物を置くスペースがあるか確認 |
| 設備 | インターホンやエアコン、トイレなどに問題はないか確認 |
| 防音性 | 外の音や他の住民の音が気にならないか確認 |
| 傷や汚れ | 目立つ傷や汚れがある場合は事前に写真をとっておく |
| セキュリティー | オートロックや防犯カメラはあるか確認 |
| 交通 | バス停や駅は近くにあるのか確認 |
| 周辺施設 | コンビニやスーパーなどが周辺にあるか確認 |
内見の時には、室内ばかりに目を向けがちです。周りの騒音がうるさかったり、スーパーなどが近くになかったりして不便な生活となる可能性もあります。内見の時には室内だけではなく、ぜひ周辺環境もチェックするようにしましょう。
契約時の注意点(敷金・礼金、更新料、契約期間など)
内見なども終わって賃貸マンションや賃貸アパートの契約をしようとするとき、賃貸借契約書を交わします。
賃貸借契約を交わす時に確認するべきいくつかの注意事項がありますので、下記の表を参考にするようにしましょう。
| チェック項目 | 確認事項 |
|---|---|
| 敷金・礼金 | 物件によって変動があるので確認 |
| 契約期間 | 契約期間は1年なのか、特別していはないのか確認 |
| 更新料 | 更新料は毎年かかるのか、いくらかかってくるのか確認 |
| 家賃の金額 | 家賃の金額に不明な点はないか確認 |
| 支払い方法 | 家賃の支払い方法は毎月振込なのか、口座引き落としなのか確認 |
| 退去予定の期間 | 次に引っ越す場合はいつまでに言えばいいのか確認 |
| 違約金 | 早期引っ越しや禁止行為などによって違約金が発生するか確認 |
賃貸借契約書によっては、その他にも特約などが設けられている場合もあります。
賃貸借契約を交わす時に気になる点などがあれば、その都度確認するようにしましょう。
荷造りの計画

引っ越しが決まった場合、荷造りの計画を始めるのは3週間〜1ヶ月前に準備をするケースが多いようです。
引っ越しの荷造りには時間がかかりますので、引っ越し直前になって慌てないためにも、余裕をもったスケジュールを組むようにしましょう。
荷造りスケジュール(いつから何を始めるか)
荷造りのスタートの目安としては、1ヶ月前から始めるのが理想です。以下に荷造りのスケジュールを紹介いたします。
| 引っ越し前の期間 | 主なやること |
|---|---|
| 1ヶ月前 | 不用品の処分と荷造りの準備 |
| 2週間前 | 普段使わない物の荷造り |
| 1週間前 | 日用品と貴重品の整理 |
| 前日 | 最終チェックと荷物の確認 |
引っ越し1か月前:不要品の処分と荷造り準備
自宅に不用品がある場合、早めに処分をおこないましょう。いるものといらない物、普段使う物とあまり使わないものを事前にある程度分けておくことで、引っ越しの準備をスムーズに進めることが可能です。
引っ越し2週間前:普段使わない物の荷造り
普段使わない食器や洋服、本や雑貨などは引っ越し2週間ほど前にダンボールに詰めます。どのダンボールに何を詰めたか分かるように、ダンボールにそれぞれペンで内容を書いておくと、後で整理がしやすくなります。
引っ越し1週間前:日用品と貴重品の整理
引っ越しの1週間前になると、普段お使いの日用品をダンボールに詰める作業に入ります。日常着ている洋服やお使いの食器、キッチン用品や小型の家電などもこのタイミングでダンボールに詰めていきます。
場合によっては直前で使う物もあったりするので、ダンボールのふたを開けた状態にしておくのがおすすめです。
引っ越し前日:最終チェックと荷物の確認
引っ越し当日は業者との打ち合わせなど、何かと慌ただしくなります。引っ越しの前日に家の中に残っている物がないかを確認し、引っ越し当日の時間やダンボールの搬入経路なども事前に確認しておくと、引っ越し当日の流れがスムーズに進みます。
梱包材の種類と選び方
荷物を梱包するのにかかせないのがダンボールです。重い家電を入れたり、小さな雑貨を詰めたりするケースも多いかと思います。
準備しておきたいおすすめのダンボールは以下の3つです。
| ダンボールの種類 | おすすめ内容 |
|---|---|
| 記入欄あり | 何を詰めたか細かく書けるので、小さい雑貨におすすめ |
| ハンガーかけあり | 洋服をそのままハンガーにかけて運びたい時におすすめ |
引っ越し業者によってはこれらのダンボールを準備しているところもあります。自分でダンボールを準備するのが大変と思われる方は、これらのダンボールがないか、事前に引っ越し業者に問い合わせてみましょう。
効率的な荷造りのコツ
いきなりダンボールに詰める前に、まずは詰める物をグループ分けしていきます。リビング・キッチン・トイレ・寝室といった具合に分けて梱包していき、効率よく荷造りを始めていきましょう。
不要品の処分方法(リサイクル、寄付、不用品回収業者など)
大型の家具や家電などは粗大ゴミとして出す必要があります。ご自身で処分できない場合は自治体の回収業者に粗大ゴミの回収の依頼を出さなければなりません。
回収業者によっては回収に来るスケジュールが決まっているところもありますので、早めに連絡するようにしてください。
また、冷蔵庫と洗濯機、エアコンとテレビはリサイクル法の対象となっていますので、粗大ゴミとして出すことができません。引取り場所に持っていくか、場合によっては買取業者などに引取りをお願いするのもよいでしょう。
引っ越し当日の流れ
引っ越し当日は引っ越し業者との打合せや近隣へのご挨拶など、何かと慌ただしくなります。
以下の表を参考にして、スムーズに引っ越し作業を進めるようにしましょう。
| 引っ越し当日にやること | 確認事項 |
|---|---|
| 引っ越し業者との打合せ | 作業時間・作業の流れを確認 |
| 荷物の搬出・搬入の準備 | どの荷物を運ぶのか作業員に伝える |
| 近隣への挨拶 | 搬出・搬入ルートが重なる家は必ず挨拶する |
| 引っ越し業者への支払い | 現金か振込かクレジットカードか確認 |
引っ越し業者との連携方法
引っ越し業者との事前打ち合わせ
引っ越し業者には、事前に電話やメールなどで当日の作業時間や作業の流れを確認しておきます。引っ越し場所によってはトラックが入りにくい場所などもあるため、事前にトラックを止める場所などを業者に伝えておくようにします。
また、引っ越し業者によっては引っ越し当日に現金の支払いを求めてくるケースもあります。当日支払わないといけないのか、振込やクレジットカードの支払にも対応しているのかなども事前に確認しておくようにしましょう。
引っ越し当日の確認事項
あわてることがないよう、以下の点については引っ越し当日に再度確認するようにしておきます。
・荷物はすべてダンボールに詰めたか
・引っ越し作業の邪魔になるものはないか
・引っ越し業者のトラックをとめる位置は問題ないか
・近隣の方への挨拶はすませたか
・引っ越し業者への代金の支払いは確認したか
・管理会社へ退去の連絡はしたか
搬入搬出の立ち会いポイント
引っ越しの搬出については、作業スタッフがそれぞれダンボールをトラックに搬出するため、特別することはありません。作業スタッフから質問があれば答えるようにするとよいでしょう。
新居への搬入については、作業スタッフが家具やダンボールをどこに置いたらよいかたずねてきます。適切に回答できるよう、事前にどこに設置するかを想定しておくと搬入作業がスムーズに進みます。
問題発生時の対応策
引っ越しする際、いくつかのトラブルが起こるケースがあります。以下のようなよくある事例を参考にし、トラブルが起こった場合は対処できるようにしておきましょう。
| トラブルのケース | 対応策 |
|---|---|
| 引っ越し業者の遅刻 | 大幅な遅刻は損害賠償の対象となるケースもあり |
| 家具の破損・故障 | 引っ越し業者負担で修理 |
| 荷物の紛失 | 貴重品は必ず自分で運ぶ |
| 追加料金の発生 | 事前に必ず見積もりを取ること |
貴重品の管理
現金や通帳などの貴重品、高価な指輪やネックレスなどはダンボールに詰めてはいけません。引っ越し業者によっては荷物を紛失した場合、保証してもらえるところもありますが、高価な品物については保証できないケースがほとんどです。
貴重品や高価な品物についてはご自身で管理しておき、引っ越しの際には自分で持ち運ぶようにしましょう。
家具家電の配置
引っ越しの日に新居へ荷物を運ぶ際に考えなければならないのが、家具や家電の配置です。ソファーや冷蔵庫、洗濯機やテレビなどを旧居から新居へ運ぶ場合、どこに配置するか事前に決めておかないと、引っ越しの作業スタッフがそれぞれどこに配置したらよいか困ってしまいます。
スムーズに引っ越しの作業を進めるためにも、家具や家電の配置はあらかじめ決めておくようにしましょう。
近隣への挨拶
引っ越しする場合、原則として、旧居・新居どちらも近隣の方々へは挨拶をしておくべきです。ただし、特別近所付き合いや面識がなかったり、女性のひとり暮らしであれば防犯の関係もありますので、挨拶は状況に応じておこなうとよいでしょう。
旧居での最終確認
不要なゴミが残っていないか、荷物の運び忘れがないかなど、引っ越しが完了した後は旧居を最終確認しておきます。
また、退去の手続きの時に不動産会社からクリーニング代や修繕の費用を請求される可能性もあるため、できるだけ旧居をキレイに清掃するようにしましょう。
新居での作業
どの荷物をどの部屋におくのか、引っ越しの作業スタッフへ指示を出します。大きい家具や家電は後で移動するのが大変なので、できるだけ正確な位置に置くようにします。
ダンボールについては当日使用する物からあけていきます。急ぎでない物については、後日落ち着いてからあけるようにしましょう。
引っ越し後の手続き

引っ越し後、役所でおこなう公的な変更手続きと、生活に必要なその他の変更手続きをおこないます。
公的手続きの完了
住所変更の手続きや役場への届出など、引っ越し前後におこなう公的な手続きもたくさんあります。以下の表を参考にして、手続きのもれがないようにしましょう。
| 引っ越し前後の手続き | やり方 |
|---|---|
| 転出届 | 旧居の自治体で転出証明書を受け取る |
| 転入届 | 新居の自治体で転出証明書を提出 |
| 運転免許証の住所変更 | 最寄りの警察署・免許試験場で変更手続き |
| 印鑑登録の変更 | 新居の自治体で手続き |
| 年金手帳の住所変更 | 勤務先で手続き。マイナンバーと紐付きなら原則不要 |
| マイナンバーカードの住所変更 | 新居の自治体で手続き |
転出届・転入届の提出方法と必要な書類
引っ越しをして異なる市町村に住所を移す際には、旧居・新居それぞれの自治体に転出届・転入届を提出しなければなりません。同一の市町村であれば転出届を提出する必要はありません。
転出届・転入届の提出方法と必要な書類について解説いたします。自治体によっては手続きの流れが異なる可能性もありますので、旧居・新居それぞれの自治体のホームページを必ず確認するようにしましょう。
転出届の提出方法
主な提出方法として、以下の4つが対応可能です。
1.窓口での手続き
2.郵送での手続き
3.マイナポータルでの手続き
4.代理人による窓口での手続き
基本的には、現在お住まいの市区町村の窓口で手続きをおこなうケースがほとんどかと思われます。引っ越しの14日前〜引っ越し当日までに転出届の手続きが必要ですので、忘れずに手続きをおこないましょう。
また、自治体によっては郵送やマイナンバーカードを利用した手続きに対応しているところもあります。忙しくて自治体の窓口になかなか行けず、郵送やオンラインでの手続きを希望される場合は、お住まいの自治体に確認してみてください。
転出届に必要な書類
転出届の手続きに必要な主な書類は以下のとおりです。
・本人確認書類(免許証、パスポートなど)
・マイナンバーカード(お持ちの場合)
・委任状(代理人が手続きする場合)
代理人が手続きする場合、委任状が必要です。委任状については、各自治体のホームページからダウンロードするようにしてください。
転入届の提出方法
転入届の提出は新しい自治体の役場に直接行く必要があります。転入届については郵送やオンラインでの手続きはできませんのでご注意ください。
転入届に必要な書類
転入届に必要な書類は以下のとおりです。
・転出証明書(旧自治体で転出届を出した時にもらえる)
・本人確認書類(免許証、パスポートなど)
・マイナンバーカード(お持ちであれば)
・委任状(代理人が手続きする場合)
問題がなければ、新居の自治体で書類が受理されて手続きは完了です。
運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更は、最寄りの警察署もしくは運転免許試験場で手続きをおこないます。運転免許証の住所変更をおこなわなければ、身分証明書として認められなかったり、道路交通法違反として罰金を求められる可能性もあります。
運転免許証とマイナンバーが記載されていない住民票を持っていき、早めに住所変更をおこなうようにしましょう。
印鑑登録の変更
旧住所で印鑑登録しているのであれば、変更手続きが必要です。
・旧住所:旧住所で転出届提出時に自動で廃止
・新住所:実印と身分証明書を持っていけば即日登録
印鑑登録は住宅を購入したり、自動車を購入したりする際に必要となります。後日あわてることがないよう、忘れずに手続きをおこないましょう。
年金手帳の住所変更
会社員の方や公務員の方など、厚生年金に加入の方であれば、勤務先に住所変更の連絡をすれば特別手続きは必要ありません。自営業者や農業をされている方であっても、マイナンバーと年金情報がひもづいているような方も手続きは原則不要です。ほとんどの方は年金手帳の住所変更の手続きは不要ですが、不安な方は新居の自治体へ確認を取るようにしてください。
マイナンバーカードの住所変更
新居の自治体へ転入届を提出する際に、マイナンバーカードの住所変更手続きも同時におこないます。マイナンバーカードの裏面に新住所を記載してもらえます。同居の家族がいる場合は、家族全員分の住所変更手続きもおこないましょう。
生活基盤の構築
公的な手続きをすませたら、今度は生活に必要な各種手続きをおこないます。
主な手続きは以下の6つです。
| 引っ越し前後の手続き | やり方 |
|---|---|
| インターネット回線の契約 | 既存の回線を引き継ぐか、新規で契約するか |
| NHKの住所変更 | NHKのホームページから手続き |
| 銀行口座の住所変更 | 取引銀行に電話などで直接確認 |
| クレジットカードの住所変更 | クレジットカード会社のマイページ等で変更 |
| ガス・電気の開通 | ガスは開通の立ち会いをする。電気の開通は不要。 |
| 水道の開通 | 開通手続き不要。そのまま使用可能。 |
インターネット回線の契約
旧住居にてインターネット回線を利用している場合、回線契約に応じて変更手続きが必要です。
| インターネット回線の内容 | 引っ越し後の手続き |
|---|---|
| 光回線 | 変更手続き・回線工事が必要 |
| ホームルーター(置き型Wi-Fi) | 地域によって手続きが必要 |
| モバイルルーター | 手続きは原則不要 |
インターネット回線の種類と選び方
住居の種類によってインターネット回線の選び方は異なります。以下の表を参考にしてください。
| 住居の種類 | おすすめインターネット回線 |
|---|---|
| 戸建て | 光回線 |
| マンション | 光回線(対象外ならホームルーター) |
| アパート | ホームルーターもじくはモバイルルーター |
戸建て:2階建ての場合にモバイルルーターなどを使用すると、電波が届かなかったりするケースもあります。迷わず光回線を契約することをおすすめします。
マンション:光回線が対応しているなら、速度が安定している光回線を契約しましょう。対象外の場合は光回線の次に速度が早い、ホームルーターがおすすめです。
アパート:光回線は対象外のケースがほとんどです。電波が入る地域なら、ホームルーターをおすすめします。
インターネットプロバイダーの比較ポイント
プロバイダーの比較ポイントは以下の3つです。
・回線の対応エリア
・料金やオプション
・通信速度
場所によっては回線が対象外のエリアもあります。契約する前に、お住まいの地域が回線エリアの対象となっているか確認します。
次に料金やオプションを確認します。プロバイダーによってはお持ちのスマホとセットで契約することで、インターネット回線が割引の対象となる会社もあります。また、光回線の工事費が無料になったり、高額なキャッシュバックを提供しているところもありますので、そういったプロバイダーを選ぶのもよいでしょう。
最後に通信速度も検討します。プロバイダーによって提供している通信速度が違いますので、ストレスなく通信回線を利用したいのであれば、高速通信に対応しているプロバイダーを選ぶようにします。
インターネット回線の契約手続き
ホームルーターやモバイルルーターであれば、回線工事の必要はありません。ところが、光回線の契約から開通までは、ある程度の期間がかかります。以下の表を参考にして、早めに手続きをするようにしましょう。
| 必要な手続き | 注意事項 |
|---|---|
| 事業者・プロバイダーを決める | 通信エリアや料金、通信速度も比較する |
| 通信プランを選ぶ | 通信し放題か、制限をつけるのか選ぶ |
| オプションを選ぶ | ひかり電話やテレビ回線もセットで契約するのか |
| 契約する | インターネット、電話もしくは店頭で申し込む |
| 工事の予約をする | 屋内工事と屋外工事があるので早めに手続きする |
| 工事を行う | 立ち会いが必要。工事が終わるまで在宅 |
| ルーターの設定をおこなう | 説明書をみながら設定。事業者がやってくれることも。 |
| パソコンやスマホと接続する | それぞれIDやパスワードを入力して接続する。 |
開通工事の流れと注意点
光回線の開通工事の流れと注意点は以下のとおりです。
・場所によっては対象外の地域がある
・集合住宅は管理会社の許可が必要
・原則として光回線の工事の立ち会いが必要
・受付に時間がかかるので、早めに工事の予約する
山間部や郊外などでは光回線工事の対象外地域の場合がありますので、注意が必要です。
マンションなどの集合住宅では、管理会社の許可がなければ工事ができませんので、許可をとっておくようにしましょう。
また、光回線の工事の際には立ち会いが必要です。工事当日のスケジュールは空けておかなければなりません。
工事の予約をとるのにも時間がかかります。早めに予約をするようにしましょう。
NHKの住所変更
NHKのホームページにアクセスし、住所変更の手続きをおこないます。NHKは引っ越しをしても自動解約されることはありません。それどころか、旧住所と新住所で二重の受信料が発生してしまう可能性もあります。引っ越し後は速やかにNHKの住所変更の手続きをおこないましょう。
銀行口座・クレジットカードの住所変更
銀行口座については取引銀行へ確認、クレジットカードについてはカード会社のホームページにアクセスし、マイページ等にログインした上で住所変更をおこないます。各種郵送物が届かなくなる可能性もありますので、早めに手続きをするようにします。
ガス・電気の開通
ガスの開通については、ガス会社との立ち会いが必要です。不動産会社からの指示に従い、ガス会社と連携をとって開通手続きをおこなうようにしましょう。
電気については開通手続きは不要です。ご自身でブレーカーを下げれば電気を使用することが可能です。
水道の開通
水道の開通についても、基本的には立ち会い不要です。そのまま水道を使用できます。
まとめ
これまで、引っ越し前と引っ越し当日、引っ越し後にやることをそれぞれ解説してきました。
不用品の処分や梱包、近隣への挨拶や引っ越し後の公的な手続きにいたるまで、引っ越しに関してはやることが数多くあります。
手続きにもれが起こると新生活に影響が出てしまうおそれもあるため、直前になってあわてることがないよう、早めに引っ越しの準備にとりかかるようにしましょう。